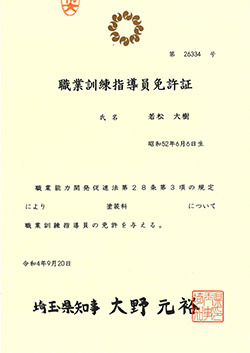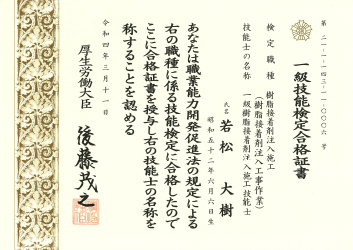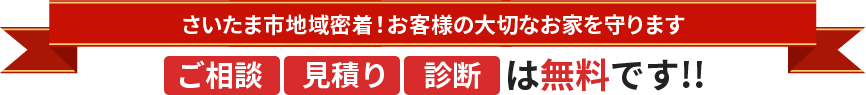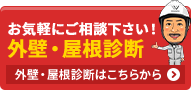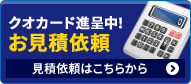刷毛の種類って?──仕上がりと効率を左右する“意外と奥深い”選び方
刷毛ってなに? 塗装と聞くと、ローラーやスプレーを思い浮かべる人が多いかもしれない。でも、細かい部分や端っこの仕上げに欠かせないのが「刷毛」なんだ。刷毛はただ塗るための道具じゃなくて、塗装の美しさを支える大事なツールなんだよ。 角や縁、段差の多いところなんかを丁寧に塗るには、刷毛の細かさや毛の質がとても重要になる。見た目はシンプルでも、選び方ひとつで塗りやすさや仕上がりに大きな差が出る道具なんだ。 主な刷毛の種類 刷毛には毛の素材や作り方でいろんな種類がある。その中でもよく使われるのがこの2つ。 中国豚毛(ちゅうごくとんもう) 天然の豚毛で作られた刷毛。毛にコシがあって、塗料の含みも良い。木部や鉄部など、表面がザラついている場所にも適している。 化繊(ナイロン・ポリエステル) 人工的に作られた毛を使った刷毛。水性塗料に強くて、塗った後の掃除がしやすいのが特長。水まわりや窓枠など、細かい場所にも使いやすい。 それぞれ得意な場面が違うから、使い分けることが大事なんだ。 用途に合った使い分け 塗る場所や仕上げたい質感によって、適した刷毛は変わってくる。 たとえば、細かい部分や、塗りムラが気になる場所には「山羊毛タイプ」の刷毛がおすすめ。毛が柔らかくて毛先が細かいから、塗装の境界線もきれいに出る。 逆に、鉄骨やフェンスなど、ザラザラした下地を塗るときは、しっかりとしたコシがある中国豚毛タイプの刷毛が向いている。塗料の含みも良くて、作業効率もアップするんだ。 刷毛の手入れと長持ちのコツ 刷毛は使ったあと、そのまま放置しておくとすぐにダメになってしまう。だから使ったらすぐに手入れをするのが基本だ。 まず、塗料が乾く前にしっかり洗うこと。水性塗料なら水、油性なら専用のシンナーなどで丁寧に洗う。そのあとは毛の形を整えて、風通しの良い日陰で自然乾燥させると長持ちする。 直射日光や湿気の多い場所に放置すると、毛が縮んだりカビが生えたりして、次に使うときに仕上がりが悪くなるんだ。手間はかかるけど、きれいに保てば何度も使えて経済的にもいいんだ。 選ぶときのポイント 刷毛を選ぶときは、いくつかのポイントを意識しておくと安心だ。 毛の素材とコシ:塗料の種類や塗る場所に合わせて、柔らかさや硬さを選ぶこと サイズと形状:広い面には幅広の刷毛、狭い隙間には細い刷毛を選ぶと塗りやすい さらに、毛が抜けにくい作りになっているかどうかもチェックポイント。安い刷毛は毛が抜けやすくて、塗った面に毛がくっついてしまうこともあるから、よく見て選ぶと失敗が少ない。 まとめ 刷毛はただの道具じゃなくて、塗装の仕上がりを左右する“名脇役”なんだ。塗る場所や使う塗料によって最適な種類を選ぶことで、ムラのない美しい仕上がりが手に入る。 ローラーやスプレーでは届かない細かい部分まで丁寧に塗れるからこそ、刷毛の存在はとても大きい。選び方も手入れも少しだけ気を配ってみてほしい。そうすることで、作業も仕上がりもグッと良くなるんだ。スタッフブログ
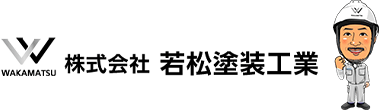

 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求 来店予約
来店予約