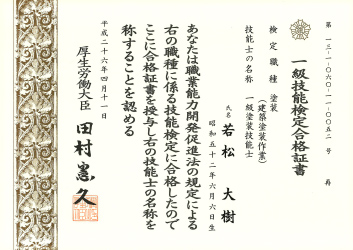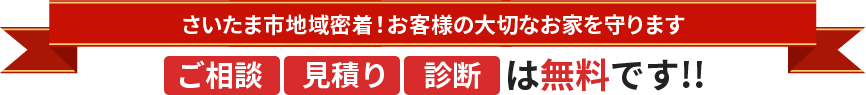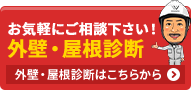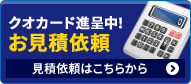アパートの塗り替えっていつ・なぜ必要?オーナー目線のポイントを解説!
アパートの外壁塗装、やらなきゃいけないって分かってるけど、正直タイミングが難しいよね… 確かに! 戸建てと違ってアパートは“資産価値”と“入居者満足”が直結するから、塗り替えのタイミングと内容がとても重要なんだ。 そもそも、どれくらいの周期で塗り替えればいいの? 一般的な目安は築後10~15年ごと。 以下の項目を要チェック! ・チョーキング:塗装部に触れると白い粉が付く ・クラック:幅1mm以上のひび割れ ・色褪せ・艶消え:新築時と比べて明らかにくすんでいる。 ・コーキングの劣化:目地が硬化・ひび割れ いずれか一つでも当てはまったら、築年数に関係なく塗り替えサインだよ。 塗装を後回しにすると、どうなる? 1.美観ダウン → 空室リスク増 2.外壁の防水性ダウン → 雨漏り・躯体劣化へ 3.修繕費が膨張(塗り替えだけで済んだところが、張り替え工事へ発展) 結果として長期の家賃収入に大打撃。だから“まだ大丈夫かな”と思っても、早めのメンテナンスが結局おトクなんだ。 アパート特有のポイントって? ✅ カラー計画は「入居者ターゲット」に合わせる ・学生向け → 明るめ・ポップな2色配分 ・ファミリー向け → 落ち着いたベージュ・ブラウン系 ✅ 共用廊下・階段も忘れず同時施工 ✅ 入居者への通知と日程調整をしっかり ✅ 足場代が大きい=外壁・屋根・鉄部を一括で(分割すると足場コストが倍増) どんな塗料を選ぶといい? シリコン 耐用年数:10~13年 向いているケース:小規模アパート・短期回収型 ラジカル 耐用年数:12~15年 向いているケース:バランス重視 フッ素 耐用年数:15~20年 向いているケース:長期保有・ハイグレード化 無機 耐用年数:18~25年 向いているケース:大規模物件・メンテ最少化 **入居者募集の“ウリ”**にするなら、耐久性+機能性(低汚染・遮熱など)をセットで提案すると差別化できるよ。 費用ってどのくらい見ておけばいい? ・20戸程度・2階建て(外壁180㎡前後) → シリコン塗装:約120~150万円 ・30戸程度・3階建て(外壁300㎡前後) → ラジカル塗装:約220~260万円 ※足場・共用部鉄部・付帯部込みの概算。 **屋根や防水が必要なら+20~30%**を想定しておこう。 業者選びのチェックリストは? 1.共同住宅の実績が豊富か 2.工事中のクレーム対応フローがあるか 3.工程ごとの写真提出・完了報告書があるか 4.オーナー・入居者向けの事前説明会の有無 5.アフター点検(1年・3年)が契約書に明記されているか まとめ:塗り替えは“空室対策+資産保全”の最強コンビ! ・築10~15年 or 劣化サインで即検討 ・足場を活かして外壁・屋根・鉄部をワンセットで ・ターゲットに合った色選び+耐久塗料で差別化 ・実績&報告体制がある施工店を選ぶとトラブル回避 アパート経営は“収益物件=ビジネス”。 だからこそ、計画的な塗り替えが入居率と将来価値を守る最重要カギだよ!お知らせ
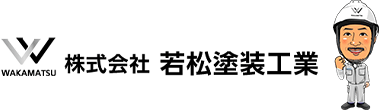

 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求 来店予約
来店予約