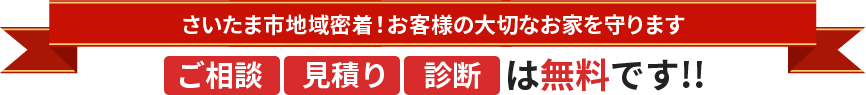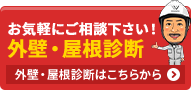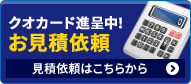2025年05月07日 更新
新築時のコーキングってどれくらいもつ?寿命とメンテナンスのタイミングを解説!
コーキングってそもそも何? コーキングとは、外壁の目地や窓枠の隙間を埋めるために使われるゴム状の充填材のことなんだ。 サイディングやALCなどの外壁はパネル同士をつなぎ合わせて施工するから、その継ぎ目(目地)ができるんだけど、そこをしっかり埋めて雨水や風の侵入を防ぐのがコーキングの役割なんだよね。 また、コーキングには建物の揺れや温度変化による膨張・収縮を吸収するクッションの役割もあるから、家の耐久性を保つためにも重要な部分なんだ。 新築時のコーキングってどのくらいもつの? 一般的に、新築時のコーキングの寿命は 「5年~10年」 くらいとされているよ! ただし、コーキングの耐久年数は 「使用されているコーキング材の種類」や「施工環境」「気候条件」 によって変わるから、一概に何年もつとは言い切れないんだよね。 コーキングの寿命を左右する要因は? コーキングの寿命は、主に 「コーキング材の種類」「施工の質」「紫外線や気候の影響」 の3つによって変わってくるよ! 1. コーキング材の種類 コーキング材にはいくつか種類があって、それぞれ耐久性が異なるんだ。 アクリル系コーキング(寿命:約3~5年) 主に室内で使われるタイプ。外壁にはあまり向いていなくて、屋外では劣化が早い。 ウレタン系コーキング(寿命:約5~7年) 強度があり塗装も可能だけど、紫外線に弱く、劣化が早いのが難点。 シリコン系コーキング(寿命:約10~15年) 耐水性・耐久性が高いけど、塗装が乗らないので、外壁用にはあまり使われない。 変成シリコン系コーキング(寿命:約10~15年) 外壁のコーキングとしてよく使われるタイプで、塗装ができて耐久性も高い! 新築時に使われているコーキング材は、比較的安価な「ウレタン系」や「一般的な変成シリコン系」のものが多いから、だいたい 7~10年くらいで劣化が始まることが多いんだよね。 2. 施工の質 コーキングは、施工の仕方によっても寿命が変わるんだ。 例えば… ・下地処理が不十分 → 下地にホコリや油分が残っていると、コーキングが密着せず、剥がれやすくなる。 ・プライマーを塗っていない → コーキングの密着を良くする下地材(プライマー)を塗らないと、早く劣化しやすい。 ・厚みが足りない → 目地に対してコーキングの厚みが薄すぎると、すぐにひび割れてしまう。 新築時のコーキングは、コストを抑えるために最低限の施工がされていることもあるので、意外と寿命が短いことが多いんだよね。 3. 紫外線や気候の影響 コーキングは、紫外線や雨風の影響を強く受ける部分だから、日当たりの良い場所では劣化が早まりやすいんだ。 特に… ・南側や西側の外壁 → 直射日光を浴びやすいため、コーキングが硬くなり、ひび割れや剥がれが発生しやすい。 ・寒暖差が激しい地域 → コーキングは温度変化で膨張・収縮を繰り返すため、劣化が早まることがある。 コーキングの寿命サインは? 新築後5年を過ぎたら、定期的にコーキングの状態をチェックするのがおすすめ! 次のような症状が見られたら、そろそろメンテナンスのタイミングかも! ✅ ひび割れがある → コーキングが硬くなって弾力を失い、細かいひびが入っている状態。 ✅ 剥がれ・割れがある → 目地からコーキングが剥がれていると、隙間から水が入り込む可能性がある! ✅ 痩せて隙間ができている → コーキングが痩せて、目地の端に隙間ができていると、雨漏りのリスクがある。 ✅ 触ると粉っぽい・ボロボロしている → 紫外線の影響で劣化が進んでいるサイン! コーキングのメンテナンス方法は? コーキングの補修方法は、「増し打ち」と「打ち替え」の2種類があるよ! 1. 増し打ち(簡易補修) 古いコーキングの上から新しいコーキングを重ねる方法。 軽度の劣化なら対応可能だけど、完全に劣化している場合は効果が薄い。 2. 打ち替え(根本補修) 古いコーキングをすべて撤去し、新しく打ち直す方法。 費用は増し打ちより高いけど、耐久性がアップするので長持ちする! まとめ:新築のコーキングは10年以内にメンテナンスを! 新築時のコーキングは、一般的に「7~10年」で寿命を迎えることが多い! 特に、紫外線の影響が強い場所や、施工の質が低い場合は、5年ほどで劣化が始まることもあるから、早めの点検が大切! ✅ 5~7年を目安にコーキングの状態をチェックする! ✅ ひび割れや剥がれが見られたら、メンテナンスを検討する! ✅ 耐久性の高いコーキング材(変成シリコン系など)を選ぶと長持ち! もしコーキングの劣化が気になったら、放置せずに早めにメンテナンスをして、建物を守ることが大切!スタッフブログ
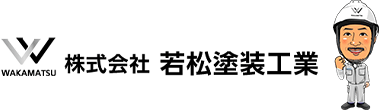

 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求 来店予約
来店予約