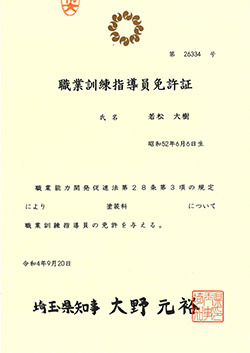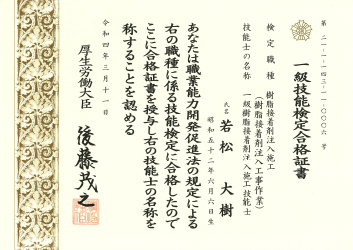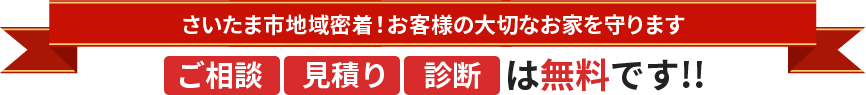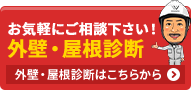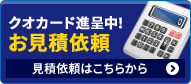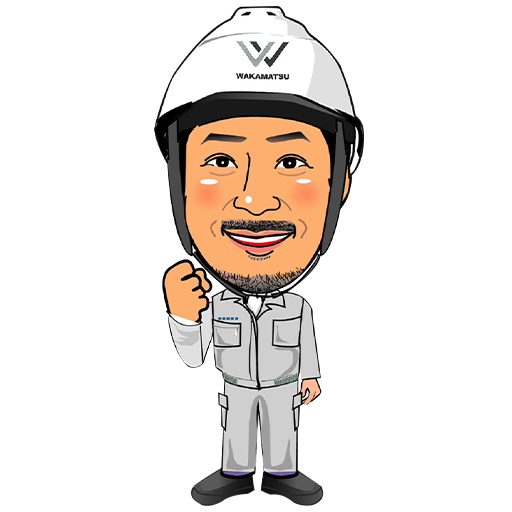
営業中心の塗装会社とは?──契約が最優先の「売るプロ」型
営業中心の塗装会社ってどんな会社? 営業中心の塗装会社は、契約を取ることを主軸にして動く会社だ。見積もりの提案力や営業トークに力を入れていて、「見た目のプレゼン」や「セールス力」で勝負するタイプが多い。素早くお客様を獲得する営業力には長けているんだ。 何が強み?どんな感じで対応してくる? 営業中心の塗装会社の強みは、スピード感と提案の多様さにある。 ・即提案力が高い:相談すればすぐに現調に来て、その場で仮見積もりと色の提案をしてくれる ・営業トークが巧み:割引やキャンペーンの案内、値引き交渉が得意で、契約に結びつけるテンポを持っている 「いま決めるとこの色が半額!」みたいな、その場で決断を促す手法が得意なイメージだ。 どんな点に注意が必要? 営業中心の塗装会社は、契約を取るために工期や施工内容が後回しになりやすい傾向がある。契約前に魅力的な口約束が多くても、実際の施工で内容が曖昧だったりコストカットの手順が不透明になりがちだ。 それに、養生や下地処理などの丁寧な工程を省略して、短期受注・大量施工スタイルになってしまう可能性も高い。結果として、仕上がりや耐久性が不満足になったり、完成後に思わぬ追加費用が発生するなんてケースもある。 施主としてどう見極める? 営業中心の塗装会社を見極めるカギは、「見積もりの中身」と「質問への回答の質」だ。 ・見積もりがざっくりしていないか:足場・高圧洗浄・下地処理・塗料・保証など、項目ごとにきちんと分かれているかをチェック ・納期や塗料、アフター対応について質問しっかり答えてくれるか:その場の回答が曖昧だったり、「後日、担当から連絡します」しか言わないなら要注意 契約前には「どこをどう養生するの?」「下塗りの種類と回数は?」「保証はどうなってる?」など、具体的な話を聞いてみるのが安心だ。 このスタイルの会社って向いてるの? 営業中心の塗装会社が向いているのは、「すぐに塗り替えたい」「見た目重視で口コミよりも価格で決めたい」「相見積もりで勝負するタイプ」の人だ。決断が速いなら、その強みを活かせる。 でも、長期的に物件を守りたいなら、「施工中心」「品質重視」の会社選びも検討する方がいい。比較してみれば、施工重視の会社は価格で劣ることがある反面、長持ちや仕上がりの美しさには手を抜かない。 まとめ 営業中心の塗装会社は、即断即決で契約を重視し、提案力と価格アピールに長けているスタイルだ。ただしその性質上、施工内容やアフターフォローが軽視されやすく、細かいところで不安が残る場合もある。 見た目の良さや価格を重視したいなら、営業型が向いている。だけど、塗り替えの質や耐久性を大事にするなら、見積もりと説明の中身をチェックしてから、施工重視の会社との比較もしてほしいんだ。スタッフブログ
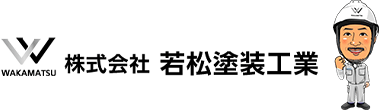

 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求 来店予約
来店予約